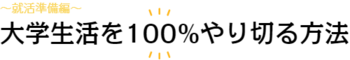テレワーク、リモートワーク、在宅勤務の違いとは
テレワーク、リモートワーク、在宅勤務は、いずれも新しい働き方として多くの企業で導入されていますが、それぞれの意味や違いを明確に理解している人は少ないかもしれません。本記事では、それぞれの定義や特徴、メリット・デメリットについて解説します。
テレワークとは?
テレワークは、自宅やコワーキングスペース、カフェなどのオフィス以外の場所で、情報通信技術(ICT)を利用して仕事を行う働き方を指します。語源は「tele(遠く)」と「work(働く)」の組み合わせです。厚生労働省では、「時間や場所にとらわれず柔軟に働ける」と定義されており、ICTの活用を強調しています。
テレワークには、以下の3つの形態があります。
・在宅勤務: 自宅を拠点に仕事を行う形式。
・モバイルワーク: 出張中や移動中など、場所に縛られず働くスタイル。
・サテライトオフィス勤務: 本社から離れたサテライトオフィスや共有オフィスでの勤務。
テレワーク・リモートワーク・在宅勤務の違い
テレワーク、リモートワーク、在宅勤務はそれぞれ似ているようで、微妙に異なる概念を持っています。
・テレワーク: ICTを活用し、自宅、カフェ、サテライトオフィスなど、どこでも仕事ができる柔軟な働き方を指す。
・リモートワーク: テレワークとほぼ同じ意味で使われるが、自宅での勤務を強調することが多い。
・在宅勤務: テレワークの一種であり、自宅に限定して働く形態を指す。
このように、リモートワークはテレワークと同義であり、在宅勤務はテレワークの一部として位置づけられることが多いです。
テレワークのメリット
ワークライフバランスの向上
テレワークでは、通勤時間がなくなり、その分を家族との時間や趣味に充てることができます。これにより、プライベートと仕事のバランスが改善され、生産性の向上にもつながります。
コスト削減
企業側ではオフィスの維持費や通勤手当の削減が可能です。一方で、従業員も通勤費や昼食代を節約できるメリットがあります。
多様な人材の確保
テレワークは、地理的な制約を超えて優秀な人材を確保することが可能です。育児や介護でオフィス勤務が難しい人にとっても、柔軟な働き方を提供できるため、企業にとって人材確保の手段となります。
感染症対策
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、テレワークは感染防止策として有効な手段です。通勤による密を避け、オフィスの人数を減らすことで、感染リスクを下げることができます。
災害時の業務継続
災害や緊急事態時においても、テレワークの環境が整っていれば業務を中断することなく継続することが可能です。これにより、企業はリスクに備えることができます。
テレワークのデメリット
コミュニケーションの課題
テレワークでは、対面でのやりとりが減少するため、コミュニケーションの機会が制限される可能性があります。これにより、誤解や情報の伝達ミスが発生しやすくなります。
孤独感や疎外感
一人暮らしの従業員は、オフィスでの雑談や同僚との交流がないため、孤独感を感じやすくなります。この問題に対処するために、企業はオンラインのコミュニケーションを促進する必要があります。
セキュリティリスクの増加
在宅勤務では、社外のネットワークを利用するため、セキュリティリスクが高まります。情報漏洩やデータの紛失を防ぐために、セキュリティ対策の強化が求められます。
勤務時間とプライベートの区別が難しい
自宅で働くことで、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。これにより、長時間労働に陥るリスクが高まるため、適切な労務管理が重要です。
導入コストの発生
テレワークの導入には、勤怠管理システムやコミュニケーションツールの導入コストがかかります。また、従業員に適切な作業環境を整えるためのサポートも必要です。
テレワークが可能な業界・職種・職種は?
テレワークは場所に縛られず柔軟に働ける働き方であり、さまざまな業界や職種でその導入が進んでいます。
情報技術(IT)業界
IT業界は、テレワークを導入する代表的な業界です。ソフトウェア開発やシステムエンジニアリング、データベース管理など、パソコンとインターネットさえあれば業務が進められるため、自宅やコワーキングスペースなど、場所を問わず仕事ができます。
これらの職種では、オフィスに出社する必要が少ないため、多くの企業がテレワークを標準化しています。
クリエイティブ業界
クリエイティブ業界も、テレワークが広く導入されています。デザインや執筆、映像編集などの仕事は、パソコンを使ったデジタル作業が多く、リモートでも効率的に進められるためです。
クリエイティブ業界は個人のスキルや成果が重視されるため、テレワークでも問題なく業務を行えます。
金融・保険業界
金融業界では、顧客対応や内部業務のデジタル化が進み、テレワークが拡大しています。データ分析や契約管理、財務報告など、デジタル環境で行える業務が多く存在します。
金融業界においても、業務のデジタル化が進むにつれ、テレワークの導入が拡大しています。
教育業界
教育分野でも、オンライン授業の普及によりテレワークが可能な職種が増えています。大学や専門学校、語学スクールではオンラインでの授業が標準化しつつあります。
コロナ禍を契機に、オンライン教育のニーズが急速に高まったことで、この業界でのテレワーク導入が一層進んでいます。
マーケティング・広告業界
マーケティング業界でも、リモートワークが一般的になりつつあります。マーケティングリサーチや広告の戦略策定、オンラインキャンペーンの管理などは、オンラインで完結する業務が多く、テレワークに適しています。
マーケティング分野は、成果物に基づいて評価されることが多く、リモートでもその効果を測定しやすい業界です。
カスタマーサポート・営業職
テレワークは、顧客サポートや営業活動にも適用されています。電話やオンラインチャットを通じたサポート業務や、ビデオ会議を通じた営業活動はリモートで効率的に行えます。
カスタマーサポートや営業職は、従来の対面業務に依存していた部分が徐々にオンラインに移行しており、テレワークに対応できるようになっています。
首都圏就活生の企業選びに関する意識
2024年に実施された首都圏の就活生を対象とした意識調査によると、コロナ禍での社会変革や大学のリモート講義の経験を経た現代の学生は、企業選びにおいて従来の価値基準から変化が見られています。この調査から、彼らの価値観や働き方に対するニーズが非常に多様化していることがわかりました。
ハイブリッドワークへの支持
多くの就活生が理想とする働き方は「ハイブリッドワーク」です。具体的には、67.0%の学生が、オフィス出社とテレワークを組み合わせて働くことができるハイブリッドワークを支持しています。この選択肢は、柔軟性を求めつつも、完全にリモートワークへ移行することには抵抗感を持っていることを示しています。一方、完全出社を希望する学生は14.3%と少数派であり、完全なテレワークを希望する学生はさらに少なく7.4%にとどまっています。この結果から、オフィス勤務とテレワークのバランスを取った働き方が主流になりつつあることが伺えます。
サテライトオフィスの重要性
企業が用意するテレワークの拠点、サテライトオフィスやシェアオフィスに対する関心も高まっています。81.6%の就活生が、従業員のためにサテライトオフィスなどの場所を整備している企業を魅力的だと感じていると回答しました。これは、テレワークに対応するための物理的な環境が、企業の魅力に直結していることを示しています。オフィス勤務を求める声は根強いものの、自宅以外の場所で仕事ができる柔軟な環境が高く評価されていることがわかります。
オフィス立地と環境への関心
企業選びにおいて、オフィスの立地条件も重視されています。「交通の利便性が高い都心のオフィス街」と「自宅から近い郊外のオフィス」、これら両方を重視する学生が多いです。68.4%の学生がこの2つの条件を「重視する」と回答しており、アクセスの良さが大きなポイントとなっています。加えて、「自宅近くや地方で働けるサテライトオフィスがある企業」も過半数の学生に支持されており、企業が提供するオフィスの柔軟性や快適さが求められています。
働き方に対する不安
新しい働き方が広がる中で、就活生が感じている不安も無視できません。最も大きな不安要素は、「配属先や上司によって働き方の柔軟性に差が生じるのではないか」(46.2%)というものでした。この不安は、いわゆる「配属ガチャ」に対する懸念を示しており、入社後にどのような働き方ができるかが予測できない点が問題視されています。
次に多い不安は、「入社直後からテレワークにより教育機会が不十分になるのではないか」(35.2%)というものです。新人として職場に溶け込み、適切なサポートを受けながら成長できるかが就活生にとって大きな関心事であり、テレワークが主流となる企業での教育体制に不安を感じているようです。
仕事よりもプライベート重視の傾向
就活生の働き方に対する価値観にも大きな変化が見られます。調査によると、53.1%の就活生が「仕事よりもプライベートを重視する」と回答しており、これは「プライベートよりも仕事を重視する」(24.2%)の2倍以上の割合です。これにより、ワークライフバランスの取れた職場がますます求められるようになっていることがわかります。企業側も、従業員が充実した私生活を送りながら働けるような環境整備が必要とされています。
ジョブ型雇用への関心
さらに、37.1%の就活生が「ジョブ型雇用の企業で働きたい」と回答しており、これは「メンバーシップ型雇用」(23.9%)を大きく上回る結果となっています。ジョブ型雇用とは、役割や職務内容が明確で、成果に基づく評価が行われる雇用形態です。これは、成果重視の働き方を望む学生が増えていることを示しており、企業にとっては、明確な評価基準を設けることが重要となっています。
参照元:首都圏就活生の企業選びに関する意識調査 2024<概要版>(https://soken.xymax.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/2403-job_hunting_students_survey_2024_summary-2.pdf)